若林 哲平株式会社INQ代表取締役CEO/行政書士法人INQ代表
株式会社INQ CEO / 創業期のスタートアップの融資を年間200件超13億円以上支援する認定支援機関。複数のスタートアップの社外CFOも務める他、東京都ASAC・NEXs TOKYOメンターなどのアクセラレーションプログラムのメンターを務める。
株式会社INQ
創業融資支援サービス
起業家のためのファイナンスメディア
2022.4.18
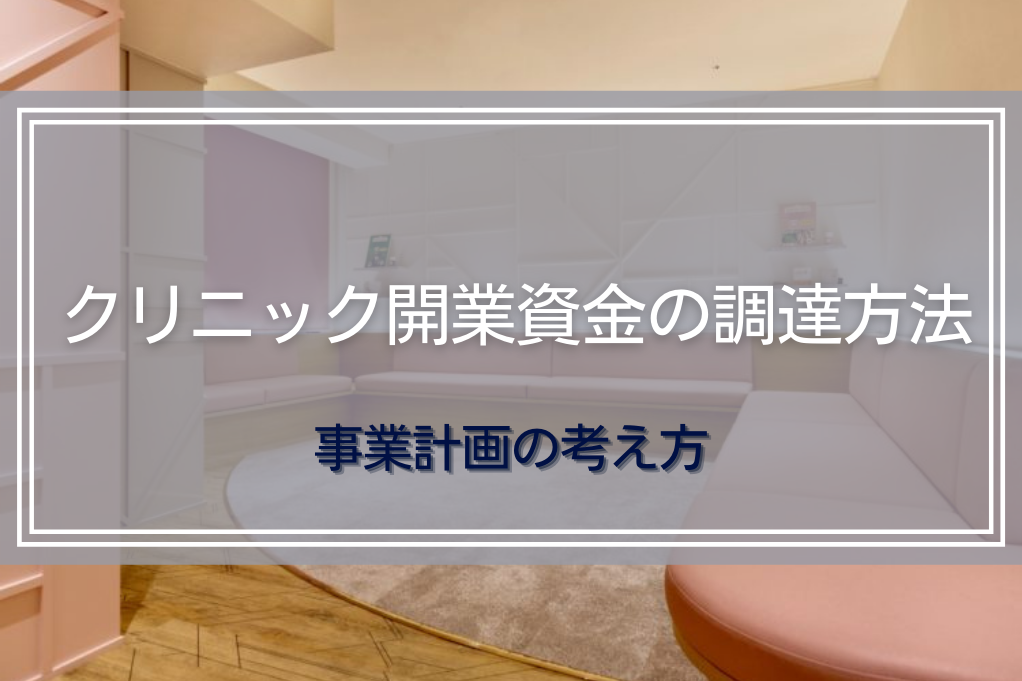 クリニック開業には物件や内装・設備工事など多くの費用がかかりますので、融資による資金調達を検討する方も多いです。
クリニック開業には物件や内装・設備工事など多くの費用がかかりますので、融資による資金調達を検討する方も多いです。
しかし初めての開業では、どのような選択肢がありどんな準備をすれば良いのか分からないですよね。
今回はクリニック開業の資金調達方法の代表例をご紹介し、費用の内訳や具体的な考え方、事業計画書の作成方法について解説します。

クリニック開業に自己資金は必要です。
自己資金なしで申し込みできる融資はありますが、開業に対する意欲を疑われ審査が不利になりやすいです。また申し込みの最低要件に自己資金額が設定されていることも少なくありません。
例えばこの後詳しく解説する日本政策金融公庫の融資制度でも、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必須要件のものがあります。
仮に自己資金0円で開業できたとしても、ぎりぎりの経営計画ではちょっとしたトラブルで資金ショートしてしまう可能性があります。予想外の出費を完全に防ぐのは難しいですから、開業を目指す早い段階から自己資金を用意しておきましょう。

クリニック開業の資金調達は複数手段があり、それぞれ特徴が異なります。
ご自身に合った手段を選べるよう、どんな選択肢があるのか把握しておきましょう。
日本政策金融公庫は取引実績の無い方でも利用しやすく、クリニックの資金調達先として比較的メジャーな選択肢の一つです。比較的低利で融資を受けることができ、開業時に活用しやすい制度もそろっています。法人格を持たない個人事業主の方でも申し込みできる点も利用しやすいポイント。
例えば国民生活事業の「新創業融資制度」では、クリニック開業にかかる設備投資やオープン後の運転資金を借り入れることができます。
融資限度額は3,000万円となっていますが、支店で決済できる金額は、創業2期以内は1,000万円が上限とされていますので、実質的に上限額は1,000万円と考えておいた方がよいでしょう。
クリニックの開業資金の場合、1,000万円の融資では足りないことがほとんどです。
その場合には、民間金融機関からの融資等で不足を補うことになります。
また政府系金融機関であるため審査が甘いというイメージを持つ方もいますが、事業計画はシビアにチェックされますので入念な準備が必要です。
民間の銀行や信用金庫の中には、クリニック開業を対象とした融資プランを用意しているところも多いです。
融資上限額や金利、担保・保証人の必要有無などは、金融機関によってまちまちです。
開業資金のほか運転資金まで借入できるケースも多く、金利などの条件が合えば有力な資金調達先となるかもしれません。
最初は、信用保証協会の保証付きの融資となるケースが多いです。また金融機関によっては税理士や経営コンサルタントの紹介、開業地選定サポートなどのサービスが付随するケースもあります。
民間金融機関は審査から融資までがスピーディーなため、迅速な資金調達が必要なシーンに向いています。
ただし無理のない返済計画を練り上げる必要があるのはもちろん、有利な条件を引き出すには交渉力も欠かせません。
クリニックの医療機器をリースする会社が、開業資金の貸し付けまで対応しているケースもあります。
リースとまとめて資金調達もできる手軽さが魅力ですが、銀行⇒リース会社と仲介する仕組みなため金利は高い傾向があります。
ただし審査基準は甘い傾向があるため、足りない資金をスピーディーに調達する選択肢としてはアリかもしれません。
地域の医師信用組合が用意するクリニック開業向けのローンも、有力な資金調達の選択肢です。医師会員の相互扶助を目的とした金融機関なので、金利や返済期間などの有利な条件が期待できます。
購入物件での開業のほか、医療機械購入資金、運転資金、自動車購入など太陽用途も幅広いです。
無担保での融資も可能なうえ、連帯保証人が原則配偶者のみとなっているのも活用しやすいポイント。
反面医師会と組合への加入が必須条件となり、県外へ転出すると追加融資が受けられないなどのデメリットもあります。
クリニック開業では政府機関や地方自治体が運営する補助金・助成金制度を活用できるケースもあります。補助金や助成金は返済の必要がないことが最大のメリットです。ローリスクで自己資金投入や借入金を減らすことができます。
例えば経済産業省が管轄する「IT導入補助金」は、電子カルテやオンライン診療システムの導入などが助成対象になります。補助率は1/2以下で、支給金額の上限は150~450万円です。
補助金を活用してWEB予約システムなどを導入できれば、業務の効率化や待ち時間短縮など運用面のメリットも大きいです。
また受付や事務のスタッフを雇い入れる場合、「トライアル雇用助成金」が活用できます。条件を満たせば一月あたり4万円の奨励金が支給され、人材採用と育成のコスト削減につながります。出産や育児で離職した方も対象になるので、クリニック勤務経験のある人材も狙えるかもしれません。

融資の申し込みをする際には、必要な資金の内訳をはっきり明示しなければいけません。
それぞれの金額はクリニックの規模や状況によって異なりますが、どのような項目があるのか把握しておきましょう。
|
設備資金 物件購入費用or家賃・契約手数料など |
クリニック開業物件の取得にかかる費用です。テナント開業の場合は礼金や仲介手数料なども含まれます。 |
|
内装施工 |
内装や照明のほか、受付・空調設備なども含まれます。 |
|
医療機器購入・リース |
診療に必要な医療機器の取得費用です。リースの場合は手数料がかかります。 |
|
什器・備品購入 |
待合室のソファーや棚、レジやタイムカードなど。 |
|
運転資金 |
開業直後から売り上げが立つまでの固定費を支払うための資金です。 |
|
広告宣伝費用 |
集患に必要なチラシ・看板、ホームページ制作などが含まれます。 |
|
スタッフ採用・研修費用 |
スタッフ募集の掲載費用、採用後の人件費、研修にかかるコストが含まれます。 |
大まかに上記の項目が開業資金に該当します。内科・外科など診療科目クリニックの規模やスタッフ数によって費用は変動しますが、基本的な項目を覚えておくと資金計画に役立つでしょう。
オープン後の運転資金や間接的に発生する費用も含まれますので、漏れの無いようにシミュレーションすることが大切です。
また、クリニックの内装費用はデザインや仕様によって変わるため、相場を把握するのがおすすめです。
〈関連コラム〉
クリニック内装の費用・坪単価相場は?格安内装工事のリスクと失敗しないコストダウンのポイント
クリニックをテナント開業する場合、物件によって初期費用や内装工事の坪単価が変わることもあります。物件探しの段階からこだわるのが、開業費用を抑えるポイントです。
〈関連コラム〉

具体的にクリニック開業の資金計画を立てるときは、まず売上目標を決めてから逆算して考えていくのがスムーズです。
具体的には、上記の順番で考えるとスムーズです。まずは、年間の売上目標を決め、必要となる患者数の目安を計算してみましょう。
| 主たる診療科 | 外来患者1人1日あたり収益額 |
| 内科 | 8,337円 |
| 皮膚科 | 5,738円 |
| 小児科 | 8,470円 |
| 整形外科 | 5,499円 |
| 耳鼻咽喉科 | 5,210円 |
| 歯科 | 9,788円 |
出典:独立行政法人福祉医療機構 2020年度(令和2年度)病院・診療所の経営状況(速報)
独立行政法人福祉医療機構の調査によると、無床診療所の外来患者1人当たりの収益額は上記のようになっています。
仮に、内科クリニックで、年間5,000万円の売上をつくる場合に必要な患者数を計算してみましょう。
5,000万円 ÷ 8,337円 = 5,997人
上記の計算で、1年間に必要な患者数は5,997人です。1ヶ月では約500人、診療日数20日間の場合1日25人が必要になります。あくまで平均なので開業地域やクリニックのコンセプトによって変動する可能性はありますが、1つの目安になるでしょう。
患者数が分かれば、クリニックに必要な床面積やスタッフ数なども割り出すことができます。クリニックの規模を最初に決めることで、テナント料や内装工事、人件費なども高い精度で試算できます。
いきなりテナント物件を探し始めるのではなく、売上⇒患者数⇒クリニックの規模の順番で、必要な資金を考えてみましょう。

開業物件の取得費用やテナント料などは、エリアによっても大きく変わります。
人口が多い都市部は集患面では有利なものの、物件の取得費用とテナント料が高額なため開業資金も増加します。目標売上を達成できたとしても、開業資金がかかり過ぎると赤字経営のリスクが高くなるでしょう。
一方、郊外エリアはテナント料や人件費を抑えられ、診療圏が広い傾向があります。しかし、診療圏内の人口が少なすぎると売上目標を達成できない可能性があり、少子高齢化で需要が減少するリスクも。
クリニック開業を検討する際は、コンセプトや目標とする売り上げと開業資金のバランスを取りながら、エリアについてもしっかり考えましょう。
また、開業エリアは、人口に対してクリニックの数が少なく、需要が大きい地域を選ぶことも大切です。日本医師会が運営している地域医療情報システム(JMAP)を使うと、地域ごとの医院・診療所の数を確認できます。

融資を受ける際必ず必要になる事業計画書の作成に頭を悩ませる方も少なくありませんが、成功率に大きく関わる重要なポイントです。
金融機関は事業計画書で、融資額の内訳や整合性、クリニックの継続性などをチェックします。奇をてらった経営計画を立てる必要はありませんが、競合との差別化やその地域で開業する理由について明確な根拠も必要です。
事業計画書の作成自体は難しいものではありませんが、事業計画やコンセプトの精度によって融資率は変わります。下記はサウナの事業計画書についてまとめたコラムですが、クリニックも基本的な考え方は同じなので、ぜひ参考にしてみてください。
〈関連コラム〉
実際に事業計画書を作成する際は、内装施工や設備投資の見積もりなどが必要になりますので、確実な融資を狙うならプロのサポートを受けるのも一つの手です。

私たち秀建は店舗内装のプロフェッショナルとして、クリニック開業をトータルサポートしています。
内装の見積もり・施工はもちろん、融資成功率98%の支援パートナーもご紹介可能です。成功報酬方式なのでリスクが少なく、補助金や助成金の申し込みサポートにも対応しています。
これまで多くのクリニック様をサポートしてきた実績もございますので、開業に関する疑問・お悩みをお気軽にご相談ください。